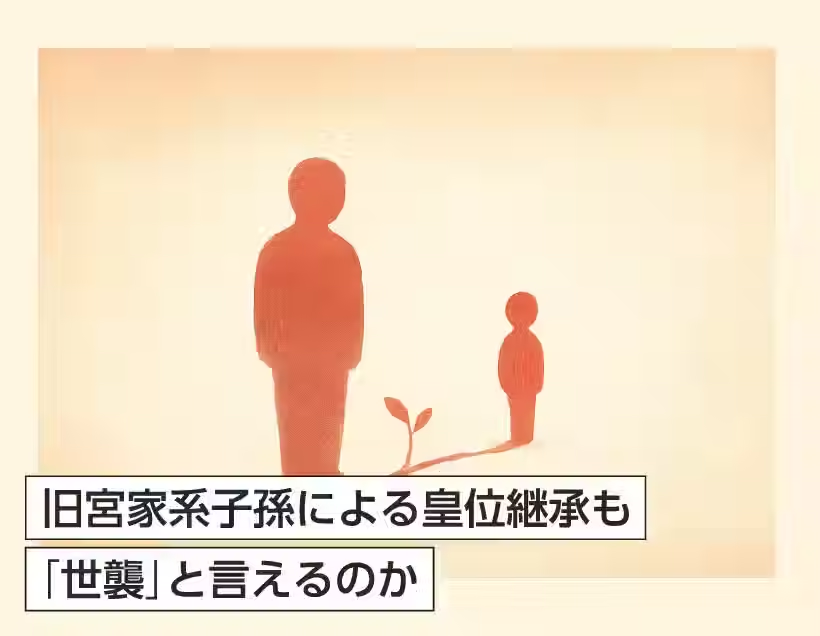「令和の天皇論」を巡る座談会記事から
- 高森明勅

- 2025年8月27日
- 読了時間: 3分

『文藝春秋』9月号に「徹底討論 ー令和の天皇論」という座談会記事が掲載されている。
参加者は思想史家の先崎彰容、
近現代史研究者の辻田真佐憲、
文芸評論家の浜崎洋介、
評論家の與那覇潤の諸氏。
皆さん、昭和50年代の生まれ。
それぞれ特色のある著書や論考を発表している。
言論界の次世代を担う論客達というポジションか。
この中で、先崎氏とは一度だけお会いしたことがある。
彼が主宰する研究会(「令和の国家像」研究会)にゲストスピーカーとして招かれた。
記事中、興味深い発言がある一方で首をかしげる部分も。
興味深い発言は例えば…。
「終戦1周年の前日、昭和天皇は、閣僚らを集めた茶話会で、敗戦について語るのに、663年の白村江の戦いでの日本の大敗を引き合いに出している。…1300年以上も前の歴史を昭和天皇は自然に口にされた。これほど長い歴史感覚で生きている…。昭和天皇が感じていた『責任』というか『歴史の重み』は、今日の我々が思うような『責任』では測れない」(先崎氏)
※この事実は早くから私が強調して来た。こうした観点を若い世代が受け継いでくれているのは嬉しい。
「権威が、『生まれながら』に皇室から発するという考えには、慎重でありたい。…今の上皇·上皇后も、慕われるのはお2人の『努力と実績』ゆえです」(與那覇氏)
「僕が恐れるのは、今のネット社会には、スマホでダイレクトにつながる疑似カリスマや疑似聖性が生まれていることです。この状態で天皇がいなくなれば、蓋が開いたコーラのように、非合理的なもの、暴力的なものが噴出してくる。…そうした歪(いびつ)なカリスマは、『時間に担保された正統な権威』で抑え込むしかない」(先崎氏)
「多種多様な権威の上に天皇が君臨していることは、日本にとって大切なことです。…社会が妙な方向に行くのを防いでくれる」(辻田氏)
「理知で考えても、国家の凝集性を担保することのできる天皇は重要です。スピノザも言うように、個人の『自由』にはその前提条件があり、それこそが『国家』です。
国民国家のドアを回すための蝶番(ちょうつがい)として、何とか皇統を守りたいですね」(浜崎氏)
首をかしげる部分については改めて。
▼追記
①8月18日発売の『週刊現代』に「天皇と皇室の危機」特集。名古屋大学准教授の河西秀哉氏、不肖高森、宗教学者の島田裕巳氏、慶應義塾大学名誉教授の笠原英彦氏、ジャーナリストの青木理氏(掲載順)の発言を載せている。
②亡母の5年祭の為に倉敷に帰郷。
私自身が祭詞を書き、装束を身に着けて、不格好ながら奉仕した。
結婚して海外に行った長女も夫のシンガポール青年と一緒に参列。
先頃、結婚していた姪が、よく笑う元気な男の子を産んでいた。
倉敷駅近くの居酒屋で中学時代の友人と50年ぶりに再会。
新聞へのコメントやテレビ出演、拙著、ネットなどで私の発言をフォローしてくれているようだ。古本屋の「蟲文庫」(美観地区)や「万歩書店」(岡山市内)なども訪れ、それぞれ収穫があった。